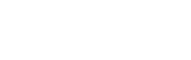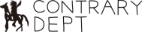Dissertation
VISVIM HARMONIOUS PROCESS : Doro-Zome (Mud-Dyeing)
泥染めを初めて取り入れたのは、もう十数年前。同じことを続けているようですが、実は、毎回の試みには少しずつ修正が加えられ試行錯誤を繰り返すことで、染色加工技術としての「泥染め」の可能性を拡げてきました。
| Category: | Processing |
|---|
| Date: | 2025.08.26 |
|---|
| Tags: | #dorozome #muddyeing #visvim #visvimharmoniousprocess |
|---|

モノづくりを繋ぐ
プロダクトを形作る素材や工法。それぞれに深い知識や高い技術を持つ職人さんがいて、その繋がりの集積が「モノづくり」であると考えています。そして、それを継続することが、お互いの理解を深めプロダクトの表現を豊かにします。けれど、こうした関係を築くことのできる方との出会いはそれほど多くはなく、それがモノづくりの難しい部分でもあります。
泥染めを初めて取り入れたのは、もう十数年前。同じことを続けているようですが、実は、毎回の試みには少しずつ修正が加えられ試行錯誤を繰り返すことで、染色加工技術としての「泥染め」の可能性を拡げてきました。単に茶色や黒色に染め上げるだけではなく、これまでの「泥染め」の歴史にはなかった、ナイロンのような化繊のプロダクトにもごく僅かなテクスチャを加えるという表現を確立してきました。
こうした取り組みには、受け継がれてきた伝統を重んじるだけではない、新たなチャレンジに対する職人さんの理解や協力が欠かせません。
着物の文化が長く続いた日本には、まだ僅かに手仕事の技術を受け継いだモノづくりが残っています。その魅力を時代にあった形に生まれ変わらせ、いまのマーケットに繋ぐこと、それが新たなモノを作る上での使命の一つだと考えています。
モノづくりを支える職人さんとの繋がり、そしてその価値を共有していただける方々との繋がり、visvimを中心とした小さなコミュニティのようなものが少しずつ育まれています。
中村ヒロキ

泥染め
古来、人間は藍、アカネ、ウコン、ベニバナなどの草木の葉や根、花、樹皮など、またコチニールカイガラムシやサラレイシガイなどの虫や貝など天然の素材から希少な染料を採取し、生活の中で使用する衣服や布類などのテキスタイルを美しく染め上げてきた。実に19世紀に入るまでの長きにわたり、天然染色の文化は世界各地で継承されてきたが、1856年に英国の化学者パーキンによって最初の化学染料モーブが発見されて以来、その染色工程の容易さと低コストにより爆発的に広まり、20世紀に入るとより褪色に強いクロム染料が普及、その影で天然染色はどんどん廃れていった。
繊維中に均一に吸収され、濃淡のないフラットな仕上がりになる化学染色に比べ、天然染色は色ムラが出やすく、また年月の経過とともに褪色しやすい。しかし、これまで常にマイナス面と見られ切り捨てられてきた、そうした天然染色の特性の中に、中村ヒロキはむしろ大きな魅力を見出している。

「均一でないからこそ、ひとつひとつに着る人の個性が反映され、繊細な奥行きを持ったキャラクターが感じられる。こうした天然染色の味わいを現代のプロダクトとして取り入れたいと考え、これまで多くの実験を行ってきました」
その試みの一つとして取り組んでいるのが、鹿児島県・奄美大島に伝わる伝統的染色技術「泥染め」を生かしたものづくりだ。
1300年以上の歴史を持つ高級絹織物として広く知られる奄美大島の伝統的な大島紬(泥大島)。その渋く艷やかな黒褐色は、奄美に自生する植物を使用し、糸を泥の中に漬け込む「泥染め」によって染め上げられてきた。

奄美の方言で「テーチ木」と呼ばれるバラ科の樹木「車輪梅(シャリンバイ)」に含まれるタンニン酸色素と、泥田の中の鉄分の化学結合を利用するもので、繰り返し染色することで絹や綿などの繊維が堅牢な深い黒色へと染まっていく。江戸時代中期にはすでに行われていたとされるこの染色法は、草木染めした着物を田んぼの中に置き忘れた(あるいは隠した)者が後日、取りに行ってみると着物が美しい黒に染まっていた、という偶然によって発見されたとも言われている。
泥染めを行うための泥田は、鉄分を豊富に含んだきめ細かい土質を持つ限られた土地にしか作ることができない。奄美大島では古代から鉄分を多く含む粘土地層の泥が分布しており、上流から水が注ぎ込みミネラルが滞留する山裾に泥田が作られる。


奄美市名瀬、島内でも最大規模の泥田が整備された「本場奄美大島紬泥染公園」。青空の下、大自然に囲まれたこの工房で、〈visvim〉では10年以上前から染色工の野崎徳和さんらとの協同により泥染め加工を行ってきた。
「土地の自然を利用した泥染めの有機的な技法、それが生み出す独特のムラや風合いに人間的な魅力を感じる」と中村は語る。「こうした加工を天然繊維だけでなく化学繊維にも施すことで、より人間らしい温かみを持ったプロダクトを生み出せないか」との思いから、泥染めの技術を応用した新たな加工の開発も試みている。

糸の状態で染める一般的な泥染めとは異なり、縫製まで済んだ製品をそのまま泥漬けすることで、服地だけでなくプロダクト全体のテクスチュアに独特の風合いが生まれる。驚くほどきめ細かくトロリとした触感の泥水を吸い込んだジャケットの重量は相当なもの。職人が膝上まで泥田に浸かり、それらを一着ずつ丁寧に泥に漬け込んでいく。乾燥させた後は洗いの作業。金属パーツなどで生地が傷つかないよう、機械を使わずタワシを使い手でこすりながら洗う。この作業を繰り返すことにより、その味わいはさらに深みを増す。古代からの自然の恵みを利用した技術を活かし、現代的な素材に新たな魅力が加えられている。
文: 井出幸亮